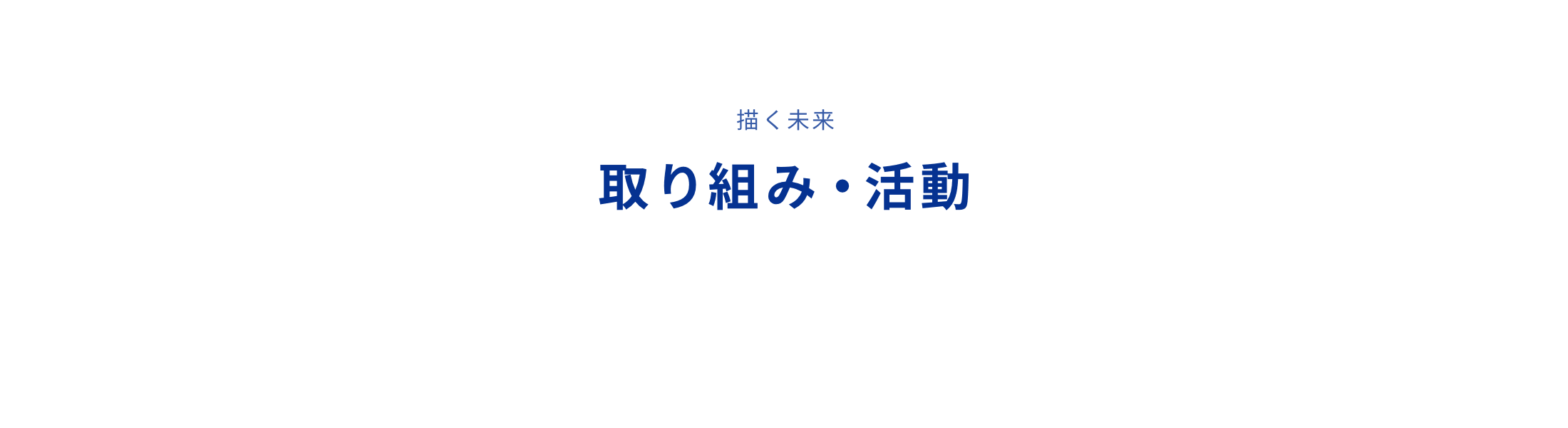ホーム![]() 描く未来
描く未来![]() 取り組み・活動一覧
取り組み・活動一覧![]() 祖父から続く農業を会社形態に転換。自社ブランド直販を確立し、人材多様性を重視した経営を推進
祖父から続く農業を会社形態に転換。自社ブランド直販を確立し、人材多様性を重視した経営を推進
キャリア・生き方
2024年12月27日
祖父から続く農業を会社形態に転換。自社ブランド直販を確立し、人材多様性を重視した経営を推進
本記事は、WOW WORLDがスポンサーを務めていたラジオ番組『森清華のLife is the journey』の放送内容の一部をテキストでご紹介するものです。
当番組は2025年3月に終了するまで、かわさきエフエム(79.1MHz)にて8年半にわたり放送。パーソナリティの森清華さんが、最前線で活躍されている企業経営者や各界のスペシャリストの“人生の分岐点”から「これからのキャリア、生き方のヒント」を紐解きます。(※文中の組織名、ゲストの方の肩書等は放送当時のものです。)
今回のゲストは、有限会社オーランドファーム 代表取締役社長 大石富一さんです。同社は北海道十勝地方に150ヘクタール(東京ドーム約32個分)という広大な土地を有し、「清流だいこん®」「十勝海霧そば®」の2ブランドを主軸に畑作農業を展開しています。
大石さんは祖父の代から続く農家の3代目で、事業承継とともに家業を会社形態に移行し、農協を通さない販売ルートを開拓して自社ブランド品の直販体制を確立。「共同体・共存・共生」を基軸にした経営をおこない、多様な立場の人々が力を出し合って作り上げる新しい農業の形を追求しています。
そんな大石さんに、キャリアに対する考え方や思いを伺いました。
当番組は2025年3月に終了するまで、かわさきエフエム(79.1MHz)にて8年半にわたり放送。パーソナリティの森清華さんが、最前線で活躍されている企業経営者や各界のスペシャリストの“人生の分岐点”から「これからのキャリア、生き方のヒント」を紐解きます。(※文中の組織名、ゲストの方の肩書等は放送当時のものです。)
今回のゲストは、有限会社オーランドファーム 代表取締役社長 大石富一さんです。同社は北海道十勝地方に150ヘクタール(東京ドーム約32個分)という広大な土地を有し、「清流だいこん®」「十勝海霧そば®」の2ブランドを主軸に畑作農業を展開しています。
大石さんは祖父の代から続く農家の3代目で、事業承継とともに家業を会社形態に移行し、農協を通さない販売ルートを開拓して自社ブランド品の直販体制を確立。「共同体・共存・共生」を基軸にした経営をおこない、多様な立場の人々が力を出し合って作り上げる新しい農業の形を追求しています。
そんな大石さんに、キャリアに対する考え方や思いを伺いました。
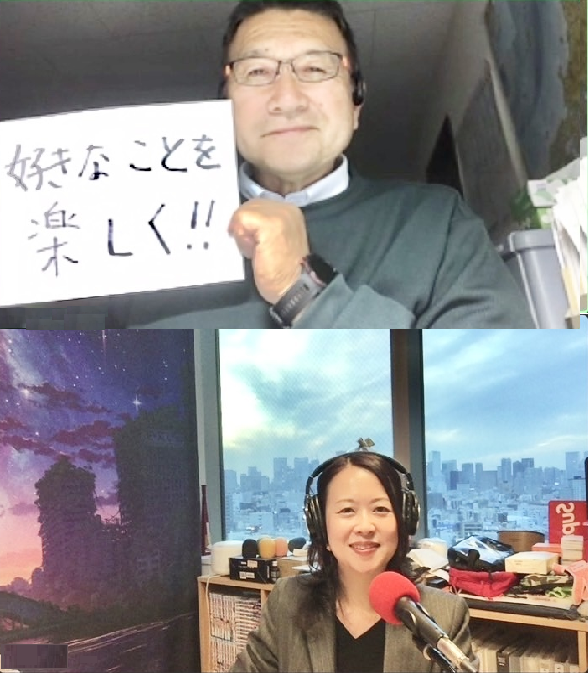
【キャリアのスタート】当初は消極的な形で家業に参加。事業承継後は会社形態による積極的な経営を展開し、自社ブランド品直販体制を確立。
森さんー 農業はお祖父様が始められたとのことですが、どのような歴史がおありでしょうか?大石さんー 北海道の農地は全国各地から移住してきた入植者たちが原生林を切り開いて作ったもので、私の祖父もそうした入植者のひとりでした。入植者には5町歩の土地が貸与され、開墾して農地にすればそのまま無償で付与されるという制度があり、祖父はそれに応募して、島根県から入植しました。5町歩は約5ヘクタールに当たります。当時は今のような機械が無い時代でしたので、それほどの広大な土地を人手で切り開いていく作業の苦労は、並大抵のものではなかっただろうと思います。
森さんー 大石さんが家業に入られたのはおいくつの頃だったのでしょうか?
大石さんー 地元の高校を出た後でした。大学受験に失敗し、他に当てもなく、農家の長男ということで、仕方なく継ぐ流れになったというのが本当のところです。
森さんー 家業を継いだ当時はどのような状況だったのでしょうか?
大石さんー 父は町会議員をやっていたこともあり外に出ることが多く、農業の仕事は母と自分に任せきりでしたが、それでも経営は譲らないという状況がしばらく続きました。業を煮やした私は「譲らないなら農業を辞める」と父に迫り、やっとのことで承諾を得ました。これからの時代は、会計を明らかにしながら外から人を雇っていかないと、農業経営は成り立たないと考えていたので、承継を機に会社を作ることにしました。以前から手伝いにきてくれていた近隣農家の方と、弟、私の3人が役員となり、「有限会社大石農産」をスタートしました。販売の面では、従来の方法では限界があると感じ、直販ルートを開拓することにしました。
森さんー 新しい体制で改革を進めていくなかで、ぶつかった壁といえばどのようなことがありましたか?
大石さんー 父の代の昭和63年から大根を作り始めていましたが、なかなか利益が出ない状況でした。初めは営業が足りないせいだと考え、販売手腕に長けた同業者の力を借り、自社の大根に「清流だいこん®」というブランド名もつけて直販ルートで販売拡大を狙いました。しかしながら結果が出ず、経営的にかなり危険な状況まで追い詰められてしまいました。そこで、商品自体に魅力がなければ、名前をつけたり販売を強化したりしても無駄だと気づき、お客様に選んでいただくためには何が必要かを徹底的に考えました。大根はまず見た目が大事で、見た目がよくないと手に取ってもらえない。手に取ってもらえても、味がよくなければ次はない。見た目がよく、なおかつ味もよい大根を作り出すためには何が必要で、何が足りていないのか。そうしたことを考えながら、土づくりから見直していきました。平成23年からはそばの栽培も始め、大根とそばの2ブランド体制にしました。
森さんー そばを作ろうと思われたきっかけは何だったのでしょうか?
大石さんー 畑作では、1つの作物を同じ土地で作り続けると土壌中の微生物の多様性やバランスが損なわれて出来が悪くなっていくので、輪作が必須です。十勝の中央部では小麦・豆・じゃがいも・ビートの輪作が一般的ですが、当社の畑は海沿いにあって気候の特性が異なるので、土地柄に合う作物ということで大根を中心に据えつつ、さまざまな輪作を試してきました。そばの輪作を試したところ非常に相性がよく、大根の品質が向上したことから、そばの栽培も本格化し、商標登録をして2つめの柱として販売することにしました。畑作は多様性を尊重しながらうまくバランスをとることが鍵。これは経営や人間社会の問題にも通じることだと思います。
家業を継承すると同時に、将来を見据えて会社形態に移行した大石さん。独自の販売ルートの開拓や農作物のブランド化など、新しい試みを積極的に展開するなかで、多様性の重要さを深く認識。社名を「大石農産」から「オーランドファーム」に変更し、多様な人々が集まって作り上げる新しい農業の形を追求していきます。
続きはこちらからお聴きいただけます。
ホーム![]() 描く未来
描く未来![]() 取り組み・活動一覧
取り組み・活動一覧![]() 祖父から続く農業を会社形態に転換。自社ブランド直販を確立し、人材多様性を重視した経営を推進
祖父から続く農業を会社形態に転換。自社ブランド直販を確立し、人材多様性を重視した経営を推進