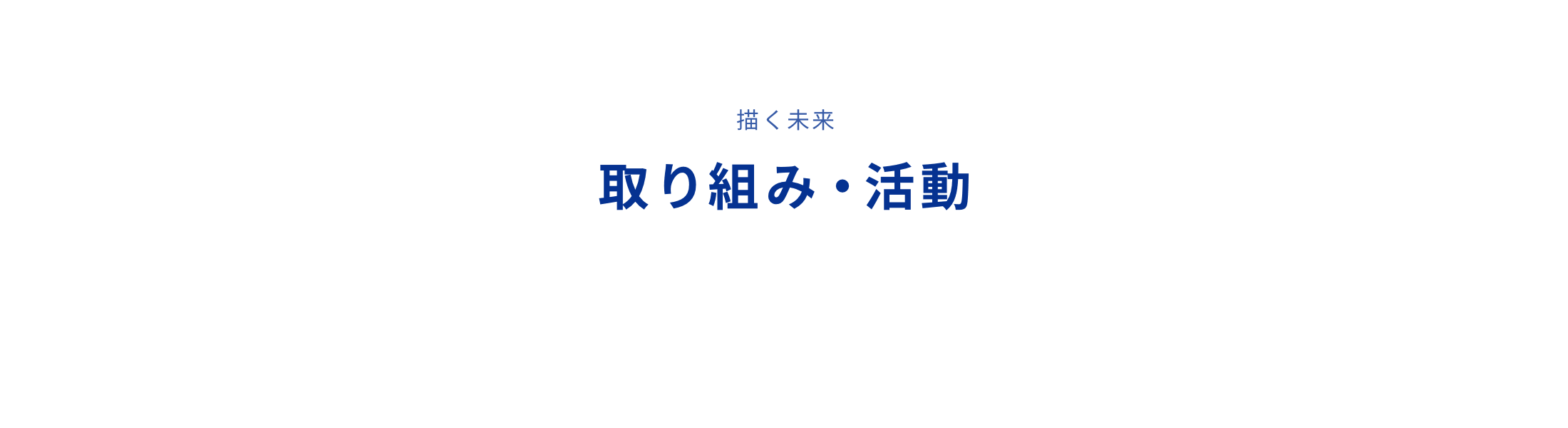キャリア・生き方
2025年02月28日
ボランティアで開発した雑草対策ロボがきっかけとなり、自動車エンジニアから農業の世界へ
本記事は、WOW WORLDがスポンサーを務めていたラジオ番組『森清華のLife is the journey』の放送内容の一部をテキストでご紹介するものです。
当番組は2025年3月に終了するまで、かわさきエフエム(79.1MHz)にて8年半にわたり放送。パーソナリティの森清華さんが、最前線で活躍されている企業経営者や各界のスペシャリストの“人生の分岐点”から「これからのキャリア、生き方のヒント」を紐解きます。(※文中の組織名、ゲストの方の肩書等は放送当時のものです。)
今回のゲストは、株式会社NEWGREEN 取締役副社長 中村哲也さんです。同社は日本の農業を世界のグリーン市場へつなぐことを使命として、水田の自動抑草ロボ「アイガモロボ」の開発製造や、次世代型農業資材の開発販売、有機米の売買などの事業を展開しています。
中村さんは日産自動車の開発統括部門でエンジニアとして23年にわたり活躍。その傍ら、東日本大震災をきっかけにして有機農法による稲作に携わるようになり、ボランティアとして「アイガモロボ」の原型を開発されました。これが大きな話題を呼び、産学連携ベンチャー・有機米デザイン株式会社(現NEWGREEN)による事業化へと結実。以来、中村さんは同社で技術面の中心人物として活躍されています。
そんな中村さんに、キャリアに対する考え方や思いを伺いました。
当番組は2025年3月に終了するまで、かわさきエフエム(79.1MHz)にて8年半にわたり放送。パーソナリティの森清華さんが、最前線で活躍されている企業経営者や各界のスペシャリストの“人生の分岐点”から「これからのキャリア、生き方のヒント」を紐解きます。(※文中の組織名、ゲストの方の肩書等は放送当時のものです。)
今回のゲストは、株式会社NEWGREEN 取締役副社長 中村哲也さんです。同社は日本の農業を世界のグリーン市場へつなぐことを使命として、水田の自動抑草ロボ「アイガモロボ」の開発製造や、次世代型農業資材の開発販売、有機米の売買などの事業を展開しています。
中村さんは日産自動車の開発統括部門でエンジニアとして23年にわたり活躍。その傍ら、東日本大震災をきっかけにして有機農法による稲作に携わるようになり、ボランティアとして「アイガモロボ」の原型を開発されました。これが大きな話題を呼び、産学連携ベンチャー・有機米デザイン株式会社(現NEWGREEN)による事業化へと結実。以来、中村さんは同社で技術面の中心人物として活躍されています。
そんな中村さんに、キャリアに対する考え方や思いを伺いました。
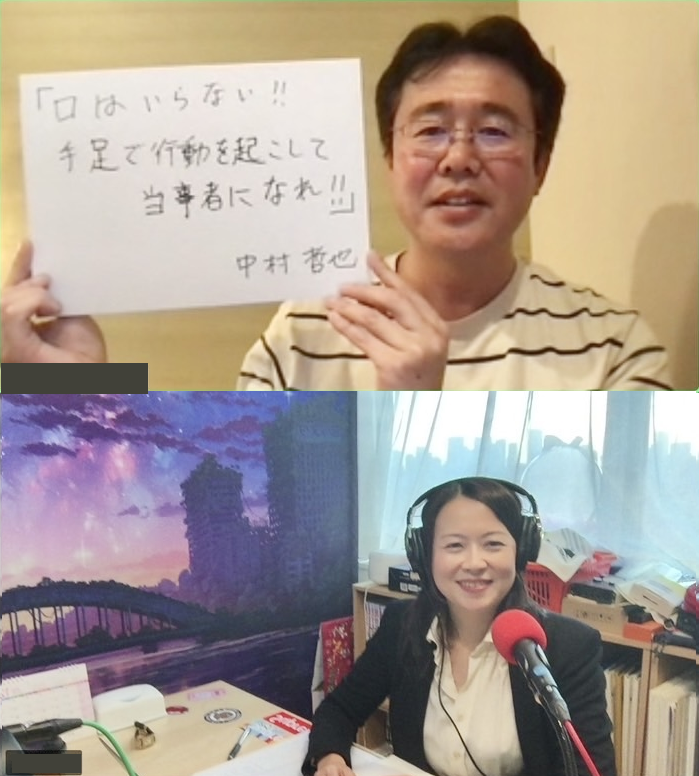
【キャリアのスタート】日産自動車で入社時から車両の開発統括部門に所属。個人的に稲作に取り組むなか、社会課題解決のため「アイガモロボ」を開発
森さんー 長年にわたりエンジニアとして活躍されている中村さんですが、エンジニアの道を志すきっかけや原点はどのようなことだったのでしょうか?中村さんー 私はいわゆるスーパーカー世代で、子供の頃はスーパーカーに熱中して、あちこちの展示会に写真を撮りに出かけたりしていました。それ以来車が好きで、自動車分野の職につきたいという考えはありましたが、就職活動を始めた頃はエンジニアにはならないでおこうと決めていて、商社など、製造業以外の会社をいろいろと回りました。当時日本ではエンジニアの地位や給料が低いと言われていて、キャリアとして魅力的に思えなかったためです。しかし、さまざまな会社を回るうちに「ものづくりをしている会社でないと新しいことは切りひらいていけない」と感じるようになり、自分が本当にやるべきなのはエンジニアの仕事だと考え直して、最終的に日産自動車に入社しました。
森さんー 日産自動車ではどのようなお仕事をされていたのでしょうか?
中村さんー 当時としては初めて車両開発の取りまとめをする部門に新卒で配属されて、それ以来ずっと同部門で仕事をしていました。カーレースでも有名な日産自動車に入社して、初めから車の開発に携われたことは、素晴らしい経験でした。
森さんー そうしたなかで、46歳のときに自動車開発から農業へと大きくキャリアを転換されるわけですが、背景にはどのような出来事があったのでしょうか?
中村さんー それまで自動車開発の仕事をやめようと思ったことはなく、40代に入っても「自動車エンジニアとしてこれからが本番」という気持ちでいたのですが、いろいろなきっかけが重なって、大きな転機を迎えることになりました。
東日本大震災の際に東京でも食料品が手に入りにくい状況が続いて、それを機に「首都圏直下型地震などの大災害が起これば、自分が食べるものさえ入手できない状況が発生しうる」という危機感を強く抱くようになりました。そうしたリスクへの対策として、大型機械や化学肥料が使えないような状況でも米や野菜を自給できるようになっておきたいと考え、翌年から山梨県で有機農法による米作りを習い始めました。有機農法では除草作業がとくに重労働で、農業人口の高齢化とともに深刻な問題になってきていました。雑草を抜くのは本当に大変な作業で、当時30代だった私でもすぐに腰が痛くなるほどでした。あるとき飲み会の席で地元農家の方から「除草作業を軽減する機械を作ってもらえないか」とお願いされ、安請け合いをしてボランティアでロボットの開発を始めることになり、それが転機の最初のきっかけとなりました。
森さんー ロボットの開発はどのように進めていかれたのでしょうか?
中村さんー 除草剤が普及する前の雑草対策について80代・90代の地元農家の方にヒアリングをしたところ、「子供を田んぼで遊ばせる」「アイガモを放つ」「イトミミズがいるところでは草が生えない」といった話を聞き、「水が濁ることで雑草が生えにくくなる」という共通したメカニズムがあることに気づきました。そして「アイガモのように水田を遊泳して水を濁らせる自動機械」というアイデアにたどり着きました。除草作業を軽減することではなく、水田に雑草が生えにくい環境にすることで課題が解決します。「物事の本質を知り、皆の一歩先、二歩先のことを考えていく」。こうした心がけが、ものづくりに携わるエンジニアにとって何よりも大切だと考えています。
森さんー ボランティアで始めたアイガモロボ開発がベンチャー企業での事業化に至るまでには、どのような経緯があったのでしょうか?
中村さんー 日産自動車の広報担当者との雑談中にアイガモロボの話をしたところ、「日産の技術者が自動運転の技術を農業に応用」という話題の動画にして公式に発信することになり、この動画が大きな反響を呼びました。私としては事業化は念頭になかったのですが、「全国稲作経営者会議の会長が日産を訪れて事業化を要請」「東京農工大学が産学連携を提案」「山形県庄内地方を拠点に課題解決型事業を展開する、株式会社SHONAIが事業化を希望」という3つの後押しが重なり、後に引けない状況になりました。このまま車づくりに関わっていたいという気持ちも強かったのですが、「これをやれるエンジニアは自分しかいない」という社会的責任の重みを感じ、日産を退社して独立を決意し、事業化に注力することにしました。
子供の頃から好きだった自動車の世界で、開発を取りまとめるエンジニアとして長年活躍された中村さん。個人的に稲作に携わるなかでボランティアとして開発した「アイガモロボ」が大きな反響を呼び、事業化へ。大企業の開発現場で培った技術と発想力をもとに、農業課題を解決するための事業へと邁進していきます。
続きはこちらからお聴きいただけます。